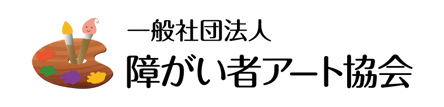まず、障がいのある方のアート作品であっても、創作された段階で著作物として保護されます。研修報告によれば、作品を創作した時点で、著作権(財産権)および著作者人格権が発生する旨が弁護士から説明されています。(参考)
具体的には、公表権・氏名表示権・同一性保持権といった著作者人格権や、複製権・公衆送信権などの財産的著作権があることが確認されています。
このため、企業や団体が障がい者アート作品を商品デザイン・広告・商品化などに利用(=コラボ企画)する際には、事前に「利用許諾契約」を結び、作者の意志と権利を守ることが大前提となります。
過去のコラボレーション企画と利用許諾の実践例
「作品登録&貸し出し」モデル/アートビリティ(および前身「障害者アートバンク」)
1980年代後半に始まった「障害者アートバンク(=後のアートビリティ)」の仕組みでは、障がいのある作家の作品を登録し、企業等へ貸し出すために著作権利用許諾契約を作家と団体が締結してストック作品を公開してきました。(参考)
このモデルでは、作品使用料を所定の貸し出し価格で企業等が支払い、そのうち約60%を作家に支払うという仕組みがあったことが紹介されています。
このように、「登録→作品貸出→使用料還元」という一連の流れが、障がい者アートを社会活用へつなぐ初期モデルとして機能していました。
商品デザイン・ブランド展開とのコラボ事例
例えばエイブル・アート・カンパニーは、作品画像の使用に関して「1回/1社/1号/1種/1年間」という使用許諾の枠を定め、非独占的使用を前提に、商用デザイン利用を含む契約形態を整備しています。
また、実際に大手百貨店とのコラボレーション企画では、2010年から続く例として、男性用下着や靴下のデザインに障がい者アート作品を採用したものがあります。(参考)
こうした事例では、作品そのものが「障がい者による」ということを前面に出さず、作品の持つ魅力・デザイン性で評価されている点も注目されます。
利用許諾契約の典型的条項
利用許諾契約においては、以下のような条項が典型的に含まれてきました(例:パラリンアートの契約書より)
-
著作権が作者(甲)に帰属することの確認
-
利用許諾の範囲(複製・販売・展示・二次著作物作成など)を明記
-
利用料・ロイヤリティの取り決め
-
第三者への再許諾・譲渡の可否
-
独占的利用か否か
-
作者の人格権の取扱い(氏名表示・改変禁止など)
こうした契約整備が、障がい者アートと企業がコラボする際の「安全な道筋」を作ってきたと言えます。
制度支援・相談窓口の整備と課題
制度面では、例えば滋賀県の資料では、「作品の著作権等はその作者である障害のある人の権利であることを明確にし、権利擁護も含めて支援」する旨が記されています。
また、障害者芸術活動支援センターによるモデル事業報告では、著作権・利用許諾・異分野との協働における権利保護などが「権利保護」章として整理されています。
しかしながら、実務では「どこまで利用を許諾するか」「作者が複雑な契約条項を理解できているか」「利用時の報酬やロイヤリティの透明性」という課題も指摘されています。たとえば、作品を企業に提供した後、どの程度作者へ情報が返ってきているかという点などが議論されています。(参考)
コラボ企画が抱える留意点
-
作品の改変や用途拡大:許諾範囲を明確にしないまま商品化・広告利用が進むと、作者の人格権(同一性保持権など)を侵害する可能性があります。
-
ロイヤリティの還元・継続性:初回使用料を払ったとしても、継続使用や派生商品利用時の報酬が不明瞭なケースがあります。
-
作者の意思・理解:契約締結前に、障がいのある作者本人(あるいは支援者)が内容を理解できている体制づくりが大切です。研修においても「どこに相談すればいいか」「交渉時のポイントは何か」がテーマとなっています。(参考)